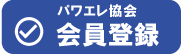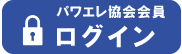電動化が進む社会と、それに取り組む技術者の学習の必要性 
マツダ株式会社 様

今なお世界的に注目され続けるハイブリッド車・電動自動車は、各メーカーが研究開発に注力しており、業界の進歩がめざましい分野である。電動化が進む業界の中でマツダは、こだわりのあるユニークな製品をもって 一際大きな存在感を放っている。
同社が法人向けパワエレ学習サブスクリプション(以下:法人サブスク)を採用しどの様に技術者育成の課題を解決しているのか、電気駆動システム開発部の堀井氏、髙島氏のお二人に話を伺いました。
―堀井さん・髙島さんが 現在どのような仕事をされているのかを教えてください。
|
|
堀井氏
|
|
|
髙島氏
|
―今までは、どの様にしてパワエレ技術の学習をされていたのでしょうか。
|
堀井氏 |
例えば本を買って勉強したり、社内で基礎的な電磁気学などの講座が用意されているのでそれを受講したり、社員同士で教えあうなどの学習をしていました。 |
|
髙島氏 |
プロジェクトレベルでのOJTもありますね。ただ、指導者の経歴やスキルに依存してしまう面もあり、皆同じレベルまでの学習をするのはなかなか難しかったかなと感じています。 |
|
堀井氏 |
学習の選択肢がいくつかある中では、パワエレ技術の学習としてはもう少し発展的な教育が欲しいと思っていたところがあります。本で読むのはどうしてもつまみ食いで断片的になりがちだったり、それ以外の取り組みでも 知識の偏りが出たりというところもあって。 また、私のように 電気駆動について経験があまりないメンバーが増えてきています。 私自身も元機械系でやっている中で電気の事が分からないながらも、パワエレ技術の教育に力を入れて的確にボトムアップしていく必要があると感じていました。パワエレ技術の専門的な知識の習得は社内のみでは得難かっただろうと思いましたね。 |
—電気業務の経験のないメンバーの課題などはあったのでしょうか。
|
髙島氏 |
そうですね、例えばシミュレーション1つをとってもパワエレならではの複合的な知識が必要です。寄生容量とか配線のインピーダンスなど目に見えない現象も自分で気づかなければいけませんが、本を読むだけだとなかなか身につかない。 あとはオシロスコープのプローブについても、誤ってグランドが浮いたところに受動プローブで測定しようとした事例があって、壊れてしまうんですけど。それは、パワエレ協会の講座を受けて知っていたので未然に防げたという事もありました。 |
パワエレ測定に関する基礎技術を幅広く、体系的に習得できる「測定技術(髙木先生)」
—技術者の育成に法人サブスクを選んだ理由を教えてください。
|
堀井氏 |
もともと教育を受けたいという人は多くいました。パワエレ協会のセミナーは講座数も多く、先ほども言ったようにパワエレ技術の専門的な知識を求めていたので、そこにマッチしたためです。また、セミナーの講師のお名前を見たら、私の使っていた本や教材を書かれた方がいらっしゃるなと思って。安心して、社内へ起案ができました。森本先生だったり、平地先生は特に印象的でした。 |
—どのような形で受講者を募集されたのでしょうか
|
堀井氏 |
枠があるので、もちろんなるべく上限まで使いたいなというのがありました。まずは募集をかけて、契約期間前半と後半に分けて希望を出してもらいました。すると、想定以上に希望数が集まり、前半分である程度枠が埋まってしまったため後半でも受講が出来るように、メンバーごとに調整をしました。 希望者が多かったのは、我々が困っている問題についてピンポイントで解決につながりそうな講座があったからではないかなと思います。募集にはHPや、ダウンロードができるエクセル形式のセミナー一覧表が役に経ちました。タイトルを確認して、必要であればHPを見て吟味してもらう形で周知をしました。 |
|
髙島氏 |
かなりバッチリ合う講座があったので、それらを一つ一つ受けていったら受講数が増えていったかなと。また、タイトルが一目でパッとわかるというのも選びやすさに繋がったのではないでしょうか。 |
セミナーについての感想とこれからの期待
—実際に受けてみての感想はいかがでしたか。
|
髙島氏 |
いかに大学で学んだとはいえパワエレは幅広い学問なので、学生時代には身に着けていない知識があって。それを見つけて学んでいきました。あとは講師がいるので質問ができる、というのが良いと思います。本を読んだだけでは自己解釈をして間違ったまま覚えてしまうので、疑問に思ったらそれを質問できる。これはセミナーの良いところだと思います。 |
|
堀井氏 |
私、横関先生のセミナーでかなり初歩的な質問をしてしまったことがあって。今思えばスッとわかるような。なんですけれどしっかりと答えてくださって。ああ、ありがたいなと思ったところです。パワエレの専門的なところをピンポイントで教えてもらえるといったところで期待通りだったし、かなり助けられたなと思います。 |
電気に苦手意識がある人でも理解しやすいと好評の「機械系技術者のためのパワエレ基礎養成講座(横関先生)」
—おすすめのセミナーなどはありますか?
|
堀井氏 |
やはり私のように、機械系でパワエレをやり始めた人には、特に横関先生の講座はおすすめできますね。 |
|
髙島氏 |
髙木先生の「測定技術」の講座は役に立ちました。先ほどの差動プローブの事もそうですが、実際に測定の仕方って学ぶ機会がなく、学ぶにしても独学になってしまう。教えてもらえても理屈まではわからない。そこをきっちりと学べるので、業務の上でも役に立ちます。あとは今岡先生の「パワーコンバータ」についての講座は、ネットで調べてもなかなか出てこない分野で、設計の知識を深められました。それから、国峯先生の「車載・パワエレ機器に見る熱対策」もよかったです。電気だけをやっていると熱についてわからないことが多く、実際に学んでみるとヒートシンク、ファンの選定など実務に役立つことが多く、知識が広がる講座でした。 |
|
堀井氏 |
セミナーの感想とは少し異なりますが、サブスクという形態で、受けたいセミナーの希望を出したら予算などの申請等もなく受講できるという手軽さがとてもよかったですね。全体の受講数増加にも影響がありました。 |
—最後に、今後のパワエレ協会への期待を、一言ずつおねがいします。
|
|
堀井氏
|
|
|
髙島氏
|
—お話をいただきありがとうございます。
パワエレ技術は幅広く、皆様のご意見をお伺いしながら毎年新しい講座を開設しています。
皆様の成長のお役に立てる様に、引き続き努めてまいります。
マツダ株式会社様が採用をしている法人向けパワエレ学習サブスクリプションはこちら