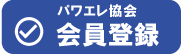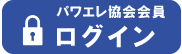DC/DCコンバータの徹底理解講座(LLCコンバータ)
| 特長 | 講師情報 |
|
LLCコンバータは簡単な回路構成で質の高いソフトスイッチング動作を実現でき、近年急速に普及しました。しかしその動作は複雑で、適切な設計のためには特別な学習が必要です。効果的な学習手段として本セミナーをご利用ください。
|
|
| 受講対象者 | |
|
・DC/DCコンバータの設計や開発に従事している方
・DC/DCコンバータの設計や開発にこれから取り組む方 ・LLCコンバータの動作を基礎からしっかり理解したい方 ・LLCコンバータの最近の技術動向を知りたい方 |
|
| 想定効果 | |
| LLCコンバータの基礎から最近の技術動向までを深く理解することができる。 |
| 内容 |
|
DC/DCコンバータは数Wから数100kWの容量まで広く実用化されています。使われる分野も家庭用から産業用まで広範囲に及んでいます。幅広い容量と様々な用途に対応して、たくさんの回路方式が研究され、実用化されてきました。それぞれの回路方式には固有の動作原理があり、独特の特性を持っています。DC/DCコンバータを使用する場合、特性をよく把握した上で回路方式を選択し、動作原理を完全に理解した上で設計する必要があります。
「DC/DCコンバータの徹底理解講座」では、DC/DCコンバータの重要な回路方式を次の6つのセミナーに分けて詳しく説明します:①フォワード型DC/DCコンバータ、②ブリッジ型DC/DCコンバータ、③電流型DC/DCコンバータと双方向DC/DCコンバータ、④PFCコンバータ、⑤LLCコンバータ、⑥DABコンバータ。それぞれのセミナーでは、各回路方式の基本となる動作原理をまず説明し、各種動作モードでの特有の振る舞いを解説します。その上で各回路方式の特徴を詳しく解説し、特性改善のための手法を紹介します。初心者の方は、各回路方式の動作原理と特徴の学習にご使用ください。ベテランの方は動作原理と特性の確認、および設計スキル向上のためにご参加ください。 |
|
LLCコンバータは、古くからあるDC/DCコンバータの回路方式ですが、近年「再発見」されて広く使用されるようになりました。主に数10Wから数100Wクラスで普及しています。しかし、その動作原理と特性は通常のDC/DCコンバータとは大きく異なり、使いこなすためには特別な学習が必要です。本セミナーではLLCコンバータの動作原理と特性を詳しく説明しますので、適切な設計を行うための技術を身につけることができます。
近年、LLCコンバータの高効率・低ノイズの特長を生かして、数kWクラスのDC/DCコンバータへの応用が期待されており、研究・開発が進展しています。本セミナーでは最近の研究・開発動向を紹介します。 |
| プログラム |
  |
|
1.LLCコンバータの概要
回路構成と特徴、開発の経緯、ソフトスイッチングの基礎、 出力電圧特性の特徴、動作周波数/出力電圧/負荷特性、
主要波形(定格負荷時/軽負荷時)、LLC方式の長所・短所、
短所とその対策、LLC専用制御ICの動向、3種類の主回路構成、
3種類の電流比較
2.LLCコンバータの動作 2-1 動作モード 2-2 各種動作:変圧器1次電圧と励磁電流、f >fr の時の動作、 電流共振としての特殊性
2-3 部分共振定番方式 2-4 ソフトスイッチング失敗動作:DT過大時、過負荷時、 制御ICでの対策
|
3.LLCコンバータの設計方法
出力電圧式の普通のDDコンとの比較、出力電圧式の導出、 出力電圧の特性、正弦波近似計算の誤差、出力電圧特性と変圧比、
設計手順、CrとLrの配分方法、設計例、巻線方法と漏れ磁束
4.新しい回路方式・制御方式 4-1 出力電圧制御範囲拡大方式 4-2 インターリーブ運転 4-3 双方向機能の実現 4-4 軽負荷時の効率改善 4-5 過電流保護 4-6 同期整流駆動回路 4-7 その他 |
| インタビュー動画 | ||||||||
 インタビュー記事 インタビュー記事 |
||||||||
| 受講の声 | ||||||||
 |
||||||||
| 日程・受講料 | ||||||||
|
||||||||
| 当日までに準備いただくこと | ||||||||
|
1.Webセミナーアプリのインストール(協会が開催前日に送付する招待メールからでもインストールできます)
2.できれば、次の平地研究室技術メモを読んでください。 No.20140529、「LLC方式DC/DCコンバータの回路構成と動作原理」 |
||||||||
| 当日の持ち物 | ||||||||
| 1.マイク機能付きパソコン 2.講義資料(事前に協会より郵送します。) 3.筆記用具 4.電卓 |
||||||||
| セミナー形式 | ||||||||
|
Zoomを利用したWebセミナーとなります。 推奨環境
Zoomの利用方法は、下記をご確認ください。 https://pwel.jp/articles/96 |
||||||||
| 主催 | ||||||||
| 日本パワーエレクトロニクス協会 | ||||||||
 |