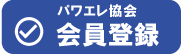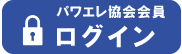| 2023年9月28日(木) 13:30~16:30 |
特長
・永久磁石同期(PM)モータの数式モデルの導出過程を回転磁界の現象理解から始めて、3相/2相変換、静止座標/回転座標(dq軸)変換、微分を伴う回路方程式の変換、モータの凸極性が及ぼす影響の数式表現を説明し、表面界磁永久磁石(SPM)モータと埋込界磁磁石(IPM)モータのdq軸回路方程式をそれぞれ導出します。
・磁気回路の原理の説明から始め、トルク発生(電気・機械エネルギー変換)の原理を詳しく説明し、PMモータのトルク式を導出します。
・PMモータの集中回路数式モデルに基づくベクトル制御の原理が完全に理解でき、さらに非線形現象を近似して数式に変換してある部分を現象と数式を組み合わせながら解説します。
・磁気回路の原理の説明から始め、トルク発生(電気・機械エネルギー変換)の原理を詳しく説明し、PMモータのトルク式を導出します。
・PMモータの集中回路数式モデルに基づくベクトル制御の原理が完全に理解でき、さらに非線形現象を近似して数式に変換してある部分を現象と数式を組み合わせながら解説します。
対象
・PMモータのベクトル制御の考え方を電磁気学の原理から出発して完全に理解したい方
・PMモータのベクトル制御技術はすでに使っているが、その基礎となるPMモータの動作原理を詳しく学びたい方
・PMモータおよびベクトル制御の改善のヒントを探している方
・電気回路の素養のある方
・参考文献1(受講特典)の1、3、5、7章などを予習しておくことが望ましい。
・PMモータのベクトル制御技術はすでに使っているが、その基礎となるPMモータの動作原理を詳しく学びたい方
・PMモータおよびベクトル制御の改善のヒントを探している方
・電気回路の素養のある方
・参考文献1(受講特典)の1、3、5、7章などを予習しておくことが望ましい。
参考文献
1. 藤本康孝、赤津観、“電気機器学の基礎理論”、3、5、7章、コロナ社
2. 河村篤男、“現代パワーエレクトロニクス”、付録BおよびC、数理工学
3. 穴山武、“エネルギー変換工学基礎論”、6.2節、丸善
4. 武田洋次、松井信行、森本茂雄、本田幸夫、“埋め込み磁石同期モータの設計と制御”、1.5節、オーム社
2. 河村篤男、“現代パワーエレクトロニクス”、付録BおよびC、数理工学
3. 穴山武、“エネルギー変換工学基礎論”、6.2節、丸善
4. 武田洋次、松井信行、森本茂雄、本田幸夫、“埋め込み磁石同期モータの設計と制御”、1.5節、オーム社
学べること
・PMモータのdq軸回路方程式とトルク発生式の原理が理解できるので、上位系であるベクトル制御の実装の設計(例えば、電流制御、PWM制御など)に役立ちます。
・その結果、モータ開発、モータ制御開発などの業務で新しいアイデアが出てくる可能性があります。
・PWELの別の講座を受講して、本講座の知見と合わせれば、独力でPMモータのベクトル制御が設計、開発、実装ができるようになります。
・その結果、モータ開発、モータ制御開発などの業務で新しいアイデアが出てくる可能性があります。
・PWELの別の講座を受講して、本講座の知見と合わせれば、独力でPMモータのベクトル制御が設計、開発、実装ができるようになります。
概要
・PMモータに関して、そもそもdq軸回路方程式とモータのトルクがどのような原理に基づいて導出されているかに関して、電磁気学の原理から出発して詳細に説明します。ただし、ベクトル制御の原理までを説明し、ベクトル制御の応用・実装などの詳細な説明は行いません。
・本講座の内容は、国立大学の電気電子関連学科の基礎電気機器学4コマ程度の講義をPMモータにフォーカスして説明するものです。
・当日のテキストは、参考文献の関連個所などを要約したものです。
・本講座の内容は、国立大学の電気電子関連学科の基礎電気機器学4コマ程度の講義をPMモータにフォーカスして説明するものです。
・当日のテキストは、参考文献の関連個所などを要約したものです。
プログラム
1.導入‐全体概要
2.SPMモータのdq軸回路方程式の導出
2-1 回転磁界と静止座標軸回路方程式の導出
2-2 3相/2相変換、静止/回転座標変換、微分を伴う回路方程式の変換
2-3 SPMモータのdq軸回路方程式
3.SPMモータのトルク式の導出
3-1 磁気回路―起磁力、磁気抵抗、磁束
3-2 電気・機械エネルギー変換―磁気エネルギー、トルク
3-3 SPMモータのトルク式-マグネットトルク
3-4 SPMモータのベクトル制御の原理と考察
4.IPM モータのdq軸回路方程式とトルク式の導出
4-1 凸極性のある回路方程式の導出
4-2 IPMモータのトルク式の導出-リラクタンストルク
4-3 IPMモータのベクトル制御の原理と考察
5.質疑応答
2.SPMモータのdq軸回路方程式の導出
2-1 回転磁界と静止座標軸回路方程式の導出
2-2 3相/2相変換、静止/回転座標変換、微分を伴う回路方程式の変換
2-3 SPMモータのdq軸回路方程式
3.SPMモータのトルク式の導出
3-1 磁気回路―起磁力、磁気抵抗、磁束
3-2 電気・機械エネルギー変換―磁気エネルギー、トルク
3-3 SPMモータのトルク式-マグネットトルク
3-4 SPMモータのベクトル制御の原理と考察
4.IPM モータのdq軸回路方程式とトルク式の導出
4-1 凸極性のある回路方程式の導出
4-2 IPMモータのトルク式の導出-リラクタンストルク
4-3 IPMモータのベクトル制御の原理と考察
5.質疑応答
講師
受講特典
日程・受講料
開催日
【ライブ配信】2023年9月28日(木)
期間
半日
時間
13:30 ~ 16:30
受講料
25,000円 (税別) / 27,500円 (税込)
当日までのご準備
1.Webセミナーアプリ(Zoom)のインストール
・インストールはこちらから。
・Zoomの仕様や推奨環境についてはこちらから。
・Zoomの利用方法はこちらから。
アプリのインストールが難しい場合、下記ボタンよりお問い合わせください。
2.参考文献1(受講特典)の1、3、5、7章などを予習しておくことが望ましい。
・インストールはこちらから。
・Zoomの仕様や推奨環境についてはこちらから。
・Zoomの利用方法はこちらから。
アプリのインストールが難しい場合、下記ボタンよりお問い合わせください。
2.参考文献1(受講特典)の1、3、5、7章などを予習しておくことが望ましい。
当日の持ち物
1.マイク機能付きパソコン
2.講義資料(事前に協会より郵送します。)
3.筆記用具
2.講義資料(事前に協会より郵送します。)
3.筆記用具
主催
日本パワーエレクトロニクス協会