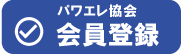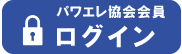設計基礎技術講座・設計編
特長
電源回路の動作から部品の選び方、アブノーマル対策まで、マンガでわかりやすく解説しています。


学習方法
STEP1:マンガをみながら、スイッチング電源の設計技術を学ぶことができます。

STEP2:各章に、設問があります。理解度を確認しながらすすめることができます。

講座概要

目次
1章
予備知識
2章
入力部(入力~整流器)
3章
入力回路(整流後~平滑部)
4章
出力トランス(T11)
5章
出力部
6章
インバータ部
7章
制御系
8章
雑音端子電圧計算
9章
アブノーマル対策設計
10章
表皮効果と近接効果
設計基礎技術講座では、スイッチング電源の設計方法について学習します。実際に販売されているコーセル株式会社製のスイッチング電源LCA75S-12(入力電圧AC100V、出力電力75W、出力電圧12V)を教材として、使用されている部品の種類や特性、各部の機能、回路定数の計算方法などについて学習します。設計基礎技術講座・設計編では、スイッチング電源の設計プロセスを理解し、回路定数の計算方法や製品の試験方法などについて学習します。
対象者
設問を解いて、じっくり学びたい技術者
中堅技術者としてレベルアップしたい技術者
受講期間・受講料
開始
お申込み日から
期間
1ヶ月
受講料
20,000円(税抜)/22,000円(税込)キャンペーン価格
法人向けパワエレ学習サブスクリプションに契約ずみの方は、法人契約専用のメールアドレスとパスワードでログインのうえ、お申し込みください。
上記以外の方はメールアドレスとパスワードでログインのうえ、お申し込みください。
上記以外の方はメールアドレスとパスワードでログインのうえ、お申し込みください。
講座詳細
1章 予備知識
17ページ


2章 入力部(入力~整流器)
27ページ


3章 入力回路(整流後~平滑部)
19ページ


4章 出力トランス(T11)
21ページ


5章 出力部
26ページ


6章 インバータ部
24ページ


7章 制御系
37ページ


8章 雑音端子電圧計算
26ページ


9章 アブノーマル対策設計
16ページ


10章 表皮効果と近接効果
14ページ


ご注意事項
講座タイトルは、予告無く変更される場合があります。
本eラーニング講座の利用は、利用者本人の個人的な範囲に限ります。